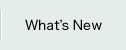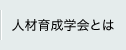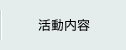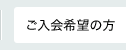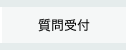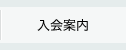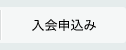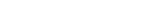人材育成学会 第13回年次大会 ~発表申し込みのご案内~
テーマ:氾濫する「グローバル」―グローバル人材育成 ver.2―
第13回年次大会は、本年12月13日(日)、中央大学多摩キャンパスにおいて開催いたします。本日、大会の概要と研究発表の応募に関する内容をお知らせいたします。以下をご熟読の上、期限内にお手続きくださるようお願いいたします。
多数のご参加とご発表をお待ちしております(参加申込みのご案内は、後日改めて行います)。
大会テーマの趣旨
人材育成は、企業組織の根幹である。今日でも、経営層の間では、組織運営の最大の課題であり続けている(NTTラーニングシステム調査 2012年)。この領域で現在、第二のグローバル化が進んでいる。
1980-90年代は「国際化」の時代と言われた。製造業の海外進出が進み、現地工場でのOJTを通した人材育成がなされた。それを反映して、日本国内で求められる人材像は「国際社会で信頼される日本人」であった。2000年代にはいり「グローバル化」の波が「人材育成」領域の中に入り始める。この時期、ビジネス・スクールの隆盛に後押しされ「グロボ・ボス(Global Boss)」が国境を超えて行き来する姿がグローバル企業組織の前景に出る。これがグローバル化の第一の波であった。
グローバル化の第二の波は2010年前後に起こる。この頃、「グローバル人材育成」なる用語が登場する。第二の波の特徴は、その抽象性、一般性、汎用性にある。「グローバル化」は、もはや、海外進出をする特定の企業、また特定の職位につく人だけの占有物ではなくなった。程度に差はあれども、あらゆる企業組織のあらゆる階層で、「グローバル性」を有した人材が求められるようになった。それゆえ、一般化された「グローバル人材」の定義が、人びとの大きな関心事となる。どこにでも適用でき転用可能な「グローバル人材」の諸特徴を把握し、涵養することが最大の課題となる。人びとは走りだした。
この第二の波の背景には、地方か都市か、あるいは組織の大小を問わずグローバルな職場環境が席巻する時代が近未来に到来するという想定がある。それゆえ、地場産業の職場慣行に新しい人を適応させるのではなく、誰もが、未だどこにも根付かない潜在的人材に対してグローバルな資質を求め、またそのためのトレーニングを探る時代になった。標的は大学におかれる。「G30国際化拠点大学」事業、「留学生30万人計画」など、もとより職場に根付いていない個人の集まりである大学がグローバル人材を育成するためのトレーニング場と化した。
問題は山積する。そもそも「グローバル人材」とは一体何か。それは定義可能なのか。存在するのか。企業組織内での着実なグローバル人材育成の方途はあるのか。氾濫する「グローバル」に踊らされないためには何をすればよいのか。この流れの中で、大学は今、こぞってグローバル化の波に乗ろうとする。大学が輩出する「グローバル人材」をどう評価するか。そもそも、大学の役割はなにか。企業組織は大学に何を期待すべきか。本シンポジウムでは、これらの問いを通して、我々が進むべき未来への指針を見出す。
期日:2015年12月13日(日)
会場:中央大学 多摩キャンパス3号館(文学部棟) 懇親会会場 同キャンパス内を予定
■所在地:八王子市東中野 742-1
■アクセス
案内図:http://www.chuo-u.ac.jp/access/tama/
最寄り駅:多摩モノレール 中央大学・明星大学駅 下車10秒
※東京・甲府方面から(JR利用)
- 中央線立川駅=(徒歩3分)⇒多摩モノレール立川北駅もしくは立川南駅=(乗車15-17分)⇒中央大学・明星大学駅
※新宿・橋本方面から(私鉄利用)
- 小田急線もしくは京王線多摩センター駅=(徒歩5分)⇒多摩モノレール多摩センター駅= (乗車6分)⇒中央大学・明星大学駅
- 京王線高幡不動駅=(徒歩3分)⇒多摩モノレール高幡不動駅= (乗車6分)⇒中央大学・明星大学駅
実行委員会
- ※委員長:野宮 大志郎(中央大学 文学部 教授)
- ※副委員長:菅野 洋介(中央大学 商学部 准教授)
■実行委員会事務局
〒192-0393 東京都八王子市東中野742-1
中央大学文学部 野宮研究室内「人材育成学会第13回年次大会実行委員会」事務局
TEL:042-674-3849 / FAX:042-674-3853
E-mail:jahrd2015chuo@gmail.com
当日スケジュール(予定)
| 9:30 | 受付 | ||
|---|---|---|---|
| 10:00 | ~ | 12:00 | 研究発表 |
| 12:00 | ~ | 13:20 | 休憩(理事会) |
| 13:20 | ~ | 15:00 | シンポジウム |
| 15:10 | ~ | 17:10 | 研究発表 |
| 17:15 | ~ | 17:45 | 総会 |
| 18:00 | ~ | 19:30 | 懇親会 |
Ⅰ.シンポジウム
テーマ : 氾濫する「グローバル」 ― グローバル人材育成 ver.2 ―
研究者、実業界で活躍する人をパネリストとしてお招きし、パネルディスカッションを予定しています。
Ⅱ.研究発表
(1)発表区分:研究発表または、事例発表に区分します。
※事例発表は、本学会の特徴を具現化するものとして毎年設けています。人材育成に関する企業やコンサルティングをとおして効果的だった事例、先進的な事例、また、特徴のある事例を紹介・報告するものです。
(2)発表者:単独発表または、共同発表に区分します。
※共同発表:発表論文を共同発表とする方で、当日発表会場に同席することが必要です。 (共同研究は、共同で研究をしている方で、発表当日の同席を義務といたしません。)
(3)発表分野:8分野に分けて募集します。
- 「グローバル化と人材育成」:グローバル化、グローバル人材とその育成に関わる領域。
- 「人材育成と社会システム」:人材育成の社会的、経済的、文化的基盤及び環境倫理を取り扱う領域。
- 「戦略と計画」:事業戦略と人的資源計画に関する領域。
- 「採用と配置」:人材の調達及び配置に関わる領域。
- 「評価と処遇」:人材の評価と処遇に関わる領域。
- 「訓練と開発」:人材の教育・訓練と個人のキャリア発達・開発に関わる領域。
- 「職場環境とメンタルヘルス」:職場環境のアメニティとメンタルヘルスの向上を取り扱う領域
- 「一般研究発表」:“人材育成”にかかわる発表または事例であれば、特に内容は問いません。自由にご応募ください。発表申込みに際しては、申込書の「キーワード欄」に必ず人材育成にかかわるキーワードをあげてください。なお,お申込みの発表内容と他の発表者の内容とを勘案して、実行委員会が、[1]から[8]の分野に振り分けさせていただくことがありますので,ご了承ください。
(4)発表時間:1人30分。(質疑応答、交代時間を含む)
Ⅲ.研究発表のお申込み
(1) 申込締切
2015年9月14日(月)必着(プログラム構成上、締切日までのお申込を厳守いただきますようお願い致します。)
(2) 申込方法
「第13回年次大会研究発表申込書」に必要事項をご記入の上、年次大会実行委員会事務局へ郵送・FAX送信、またはE-mailの添付ファイルにて、ご送付ください。
(3) お申込みにあたっての留意事項
- 上記8分野の中で適当と思われる分野を選択してください。
- お申込みされた研究発表は大会実行委員会で調整し,分野ごとに検討し審査します。その結果,発表否となる場合,あるいは申込状況に応じて発表分野の変更があることをあらかじめご了承ください。
- 研究発表として発表が決定した場合でも,送付いただいた原稿の内容によって,事例発表への変更をお願いする場合もありますので,あらかじめご了承ください。
- 第1発表者としての研究発表は1人につき1件のみとします。ただし,大会実行委員会から特に依頼された発表についてはこの限りではありません。
- 発表者は,発表の時点で会員(法人会員の構成員を含む)であることが必要です。非会員の方は,事前に学会入会の手続きをしてください(学会入会申込書は学会事務局にご請求ください)。ただし,大会実行委員会から特に依頼された発表についてはこの限りではありません。
- 大会報告論文原稿の提出時に、人材育成学会ホームページへの原稿掲載可否をお尋ねします。
(4) 発表申込書の記入について
- 発表区分は、研究発表または事例発表から選んでください。
- 発表者とは、発表会場で口頭発表する会員です。単独発表か共同発表かを選んでください。
- 共同発表者は発表時に同席することが必要です。
- 共同研究者がいらっしゃる場合は、発表申込への記載ではなく、論文提出時に、本文または、脚注で明示してください。
- 希望分野は,上記8分野から選んでください。
- キーワードは,発表に関係する10語以内を記入ください。
- 概要はなるべく詳細に書いてください。
- 教室には、パソコン(OSはWindows7、ソフトはMS-PowerPoint2010)とそれにつながっているプロジェクターを用意してあります。USBメモリーにセーブしたファイルをご持参いただけば、投影できます。なお、マックをご使用なさりたい場合は、パソコンとアダプターをご持参下さい。
- 執筆要項などの送付先は,発表者への連絡時期が9月下旬であることをご想定の上,自宅または勤務先のうち,ご都合の良い方に○を付けてください。
(5) 発表申込みの受付について
発表申込みに対しては、到着後1週間以内に受付けたことを、Eメールにてお知らせいたします(発表可否のお知らせとは別です)。そのお知らせが届かなかった場合は、恐れ入りますが実行委員会事務局までご連絡ください。
Ⅳ.発表者への連絡
- 発表者には,9月下旬に発表の可否を連絡します。
- 発表を可とされた申込者は、論文の原稿を10月20日(火)までにお送りください。(原稿締切りまでの期間が短いので、執筆要項を参考に予め原稿をご用意ください)
- 論文の原稿枚数は6枚以内とします(原則偶数ページ:執筆要項ご参照)。原稿は版下の形で,ワープロ出力したもの(またはそのコピー)を提出してください(そのままの形でモノクロ印刷します)。なお念のため,原稿のファイル(MS-WordあるいはPDF)を実行委員会事務局(jahrd2015chuo@gmail.com)宛に電子メールにてお送りください。
Ⅴ.参加申込について(10月に改めて参加申込みのご案内をいたします)
- 研究発表の有無にかかわらず、年次大会に参加される方は、参加申込が必要です。(発表申込みをされている方も、必ず参加申込み手続きをしてください)
- 参加費等(予定)
| 参加者種別 | 参加費 | 懇親会費 | |
|---|---|---|---|
| 事前申し込み | 会員 | 3,000円(資料代を含む) | 3,500円 |
| 非会員 | 7,000円(資料代を含む) | 3,500円 | |
| 学部生・大学院生 | 1,000円(資料代を含む) | 3,500円 | |
| 学部生・大学院生(非会員) | 4,000円(資料代を含む) | 3,500円 | |
| 当日参加 | 会員 | 4,000円(資料代を含む) | 4,000円 |
| 非会員 | 7,000円(資料代を含む) | 4,000円 | |
| 学部生,大学院生 | 2,000円(資料代を含む) | 4,000円 | |
| 学部生・大学院生(非会員) | 4,000円(資料代を含む) | 4,000円 |
Ⅵ.宿泊について
各自で手配いただきますよう、お願い申し上げます。
Ⅶ.今後のスケジュール(予定)
- 発表申込締切:2015年9月14日(月)
- 発表決定通知:2015年9月下旬
- 参加申込受付:2015年10月中旬から
- 論文提出締切:2015年10月20日(火)
- 事前参加申込締切:2015年12月 1日(火)
- 参加費事前支払締切:2015年12月 1日(火)